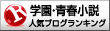三年生編 第82話(6) [小説]
「そうだなー。この中庭にはいろんな歴史があって、それは
決していい出来事じゃない。今は校舎の裏にある初代校長の
銅像、そして銅像の後釜になったモニュメントは飾り物じゃ
ないんだ。ちゃんと役割がある」
「役割、ですか」
「そう。だから、モニュメントは大事にして欲しいなーと。
それだけ」
「手紙置いちゃ……だめってことですか?」
「いや、それはいいと思うよ。想いを伝えたいっていうの
は、すっごいポジティブなことじゃん」
「はい」
「だったらいいと思う。たださ」
「うん」
僕はモニュメントの台座を指差した。
「前は、そこに女性の髪が埋まってたんだよ」
「う、うそー」
予想外の僕の言葉に怖じ気付いた渡辺さんが、じりじりっと
後ずさった。
「今はもうモニュメントの下から撤去されてて、供養は済ん
でるの。でも、マイアーはその時に一緒にいたんだよ。一部
始終を見てるんだ」
「あっ! そうか。じゃあ……」
「でしょ? 君の手紙を見た時に、イメージが重なっちゃう
だろなあと」
渡辺さんは、慌ててぱたぱたとモニュメントのところに走り
寄って、手紙を回収した。
「あの、先輩。ありがとうございますー」
「ははは。まあ、がんばって」
「はい!」
「小細工は後悔が残るよ。まっすぐトライした方がいいと思
うな」
「……。先輩はどうだったんですか?」
「ああ、しゃらとのことかい?」
「はい」
「最初の告白は向こうから。僕は最初オーケーを出さなかっ
たんだ。友達からねって、そう答えた」
「えええーーーーーっ!?」
ものすごいオーバーアクション。
何を贅沢な。そう思ったんだろうなあ。とほほ。
「でもその後僕からもコクってるから、お互いさまちゃうか
なー」
「それは、直接ですか?」
「直接だよ。しゃらから僕の時も、僕からしゃらの時も」
ほんとかなあ。そういう疑いのマナコだ。ちぇ。
「でもね、それは僕らに勇気があったからとか、そんな理由
じゃないんだ」
ふうっ。
思わず溜息が漏れる。
「あの……どして、ですか?」
「僕らは直接言葉にしないと保たなかった。僕もしゃらも、
相手の心をじっくり探る余裕なんかなかったのさ」
「意味が……」
「あはは。分かんなくてもいいよ。それは僕としゃらの間で
しか意味がないから。渡辺さんには渡辺さんのやり方がある
でしょ。それでいいじゃん。僕のアドバイスは余計なお世話
さ」
「うう」
ゆっくり中庭に踏み入って、もう一度モニュメントの側に立
つ。三本の柱を平手でぽんぽんと叩いて、話しかけた。
「恋バナの出来る庭になって良かったよ。これからもよろし
くね」
鳳凰もようこもいないけど。
それとは別に、モニュメントはこれからもぽんいちの学生た
ちをずっと見守ってくれるだろう。
そういう願いをこめながら、僕は改めてモニュメントをぱん
と叩いて激励した。
ふぁーん!!
その音が三本の柱の間で共振して……中庭をゆったりと満た
した。
その音をかき消すようにさわっと風が中庭を吹き抜けて。
満開のブルーサルビアの花を揺らす。
どんなに咲き揃っても、その青い波には圧迫感がない。
赤や黄色、ピンクのようなはっきりした自己主張は感じない。
それでも一つ一つの花は生きていて、何かを訴えているんだ
よね。
想いを口にして真っ直ぐ伝える。
伝えるには、それが一番確実だと思う。
でも、そうしないこと、そう出来ないことにもちゃんと意味
があるんだ。
そんな風に……考えよう。
「あ、じゃあ僕はこれで」
「ありがとうございますー」
「がんばってねー」
渡辺さんが、大慌てで中庭を駆け出していった。
そのあと僕も中庭を出ようとしたら、日課の見回りに来たみ
のんと鉢合わせた。
「お。みのん、おつー」
「どう?」
「すごくきれいにしてくれてるじゃん。一年生部員はほんと
に優秀だね」
「四方くんと一緒に、だいぶどやしたからなー」
「わはは! じゃなー」
「うーす」
みのんの背中に向かって手を振りながら、僕は思う。
僕には……いやきっと渡辺さんにも、結果は分かってる。
それでも、想いは溢れる。閉じ込めてはおけないってね。
決していい出来事じゃない。今は校舎の裏にある初代校長の
銅像、そして銅像の後釜になったモニュメントは飾り物じゃ
ないんだ。ちゃんと役割がある」
「役割、ですか」
「そう。だから、モニュメントは大事にして欲しいなーと。
それだけ」
「手紙置いちゃ……だめってことですか?」
「いや、それはいいと思うよ。想いを伝えたいっていうの
は、すっごいポジティブなことじゃん」
「はい」
「だったらいいと思う。たださ」
「うん」
僕はモニュメントの台座を指差した。
「前は、そこに女性の髪が埋まってたんだよ」
「う、うそー」
予想外の僕の言葉に怖じ気付いた渡辺さんが、じりじりっと
後ずさった。
「今はもうモニュメントの下から撤去されてて、供養は済ん
でるの。でも、マイアーはその時に一緒にいたんだよ。一部
始終を見てるんだ」
「あっ! そうか。じゃあ……」
「でしょ? 君の手紙を見た時に、イメージが重なっちゃう
だろなあと」
渡辺さんは、慌ててぱたぱたとモニュメントのところに走り
寄って、手紙を回収した。
「あの、先輩。ありがとうございますー」
「ははは。まあ、がんばって」
「はい!」
「小細工は後悔が残るよ。まっすぐトライした方がいいと思
うな」
「……。先輩はどうだったんですか?」
「ああ、しゃらとのことかい?」
「はい」
「最初の告白は向こうから。僕は最初オーケーを出さなかっ
たんだ。友達からねって、そう答えた」
「えええーーーーーっ!?」
ものすごいオーバーアクション。
何を贅沢な。そう思ったんだろうなあ。とほほ。
「でもその後僕からもコクってるから、お互いさまちゃうか
なー」
「それは、直接ですか?」
「直接だよ。しゃらから僕の時も、僕からしゃらの時も」
ほんとかなあ。そういう疑いのマナコだ。ちぇ。
「でもね、それは僕らに勇気があったからとか、そんな理由
じゃないんだ」
ふうっ。
思わず溜息が漏れる。
「あの……どして、ですか?」
「僕らは直接言葉にしないと保たなかった。僕もしゃらも、
相手の心をじっくり探る余裕なんかなかったのさ」
「意味が……」
「あはは。分かんなくてもいいよ。それは僕としゃらの間で
しか意味がないから。渡辺さんには渡辺さんのやり方がある
でしょ。それでいいじゃん。僕のアドバイスは余計なお世話
さ」
「うう」
ゆっくり中庭に踏み入って、もう一度モニュメントの側に立
つ。三本の柱を平手でぽんぽんと叩いて、話しかけた。
「恋バナの出来る庭になって良かったよ。これからもよろし
くね」
鳳凰もようこもいないけど。
それとは別に、モニュメントはこれからもぽんいちの学生た
ちをずっと見守ってくれるだろう。
そういう願いをこめながら、僕は改めてモニュメントをぱん
と叩いて激励した。
ふぁーん!!
その音が三本の柱の間で共振して……中庭をゆったりと満た
した。
その音をかき消すようにさわっと風が中庭を吹き抜けて。
満開のブルーサルビアの花を揺らす。
どんなに咲き揃っても、その青い波には圧迫感がない。
赤や黄色、ピンクのようなはっきりした自己主張は感じない。
それでも一つ一つの花は生きていて、何かを訴えているんだ
よね。
想いを口にして真っ直ぐ伝える。
伝えるには、それが一番確実だと思う。
でも、そうしないこと、そう出来ないことにもちゃんと意味
があるんだ。
そんな風に……考えよう。
「あ、じゃあ僕はこれで」
「ありがとうございますー」
「がんばってねー」
渡辺さんが、大慌てで中庭を駆け出していった。
そのあと僕も中庭を出ようとしたら、日課の見回りに来たみ
のんと鉢合わせた。
「お。みのん、おつー」
「どう?」
「すごくきれいにしてくれてるじゃん。一年生部員はほんと
に優秀だね」
「四方くんと一緒に、だいぶどやしたからなー」
「わはは! じゃなー」
「うーす」
みのんの背中に向かって手を振りながら、僕は思う。
僕には……いやきっと渡辺さんにも、結果は分かってる。
それでも、想いは溢れる。閉じ込めてはおけないってね。
三年生編 第82話(5) [小説]
そういや片桐先輩が最初に中庭の鎮護に乗り出した時、モ
ニュメントの真下に埋められてた宇戸野さんの髪を探し出し
てるんだ。
マイナスの念を帯びた髪が、モニュメントの抑えの力を削い
でるって言ってたなあ。
「今はもうそんなのはないよね。げっ!!」
何気なくモニュメントの中をひょいと覗き込んで、心臓が止
まるかと思ったくらい驚いた。
「て、手紙ぃ!?」
何の飾りけもない白い角封筒。口が開かないように小石が乗
せられてるってことは、封がされてないのか。
「うーん……」
みのんのことだ。ここには毎日来てるはず。
中庭の中にゴミが落ちてないかどうか、厳しく見回っている
だろう。こんな目立つものを見逃すはずがない。
つまり、昨日みのんがここを出て、今日僕がここに来るまで
の間に置かれたものだろう。
なんのため?
僕には一つしか思い浮かばなかった。
「みのんへのラブレターだろなあ」
みのんは、ここにいる間は女の子と付き合うつもりはないと
はっきり宣言している。
それでも。それでもなお、みのんに想いを寄せる女の子は跡
を絶たない。
そりゃそうさ。人の気持ちだけは、理屈じゃないもの。
好きも嫌いも感覚的なもので、それはどうしてって聞かれて
も困る。
そして。
当たり前だけど、好きってなったらどうしてもそれは伝えた
くなる。伝えないと、両想いになれるチャンスがないもの。
もちろん、伝えたって玉砕しちゃう可能性の方がずっとおっ
きいけどさ。それでも、ね。
なぜ、モニュメントの真下に置いたか。
願をかけたんだろなあ。
自由、創造、友情を象徴するモニュメントの三本の柱。
それぞれの力が決意を後押ししてくれる。
そしてモニュメントの真下に置けば、他の場所と違って見回
りに来たみのんの目に確実に留まるんだ。
確実にってことなら下駄箱の中に置くのが一番だけど、そこ
はライバルが多いし、どうしてもラブレターを仕込むアク
ションが目立っちゃう。こっそりが出来ない。
見せつけるように堂々とっていうデモンストレーションは、
そういうのが大嫌いなみのんへのアピールとしては、最低の
策になっちゃう。
「むぅ」
それはいいけど。
どうするか、だよね。
ただのゴミとして僕が処理してもいいけど、中身が何かあた
りが付くからそれはちょっとなあ。
しゃあない。見なかったことにして成り行きに任せるか。
僕は、見下ろしていたモニュメントの台座から視線を外して、
そっと離れた。
「ふうっ」
僕が中庭入り口の水盤のところまで戻ったら。
一年生の部員らしい女の子が、顔を伏せたままこそっと近付
いてきた。
色白で小柄。派手な雰囲気はないけど、かわいい系だ。
かっちんがむふふと喜びそうなタイプ。
「あの……工藤先輩」
「こんにちは。当番?」
「はい」
「ええと、ごめん。一年生の部員は人数多いから、まだ全部
は覚えきれてないんだ。君は?」
「渡辺です」
「渡辺さんか。お疲れさま」
「あの……」
「なに?」
「み、見ました?」
その子が、おずおずとモニュメントを指差す。
「あるのは分かったけど、中は見てないよ」
ほっとしたように、その子が顔を上げた。
「マイアーに、だろ?」
「う」
返事は返ってこなかったけど、多分そうだろう。
「あいつの基本姿勢は知ってるよね」
「……うん」
「それが分かってるなら、いいんじゃない?」
「そうなんですか?」
「だって、ずっと抱えてるって苦しいじゃん」
「は……い」
僕は、もう一度中庭をぐるっと見回す。
塞がった鬼門。負の感情が吹き溜まりやすい危険な場所。
羅刹門の亀裂が封鎖されたって言っても、この中庭の危険な
性質が全て解消したわけじゃない。
ここにしか捨て場のない念が吹き溜まると……。
いつかまた、不幸の再生産が始まりそうな気がする。
それは……いやだなあ。
僕は無意識にしかめ面していたんだろう。
渡辺さんが、それを気にしたみたいだ。
「あの……やっぱりダメ、ですか?」
「え?」
慌てて、振り返る。
「違うよ。君の手紙のことじゃないの。ここの、この中庭の
変な性質のこと」
「へっ?」
今度は、渡辺さんがすっとんきょうな声を上げた。
「ははは。渡辺さんは、荒れてた中庭を僕らが整備した。そ
う先輩たちに聞いてるでしょ?」
「はい」
「じゃあさ。なんでずっと荒れたままだったと思う?」
「あ……」
ぽかんと口を開けて、渡辺さんも庭を見回す。
「ははは。そういうのも一年の部員で調べてくれるとうれし
いかな。そうしたら、君たちがここを見る目が少しだけ変わ
るかもしれないね」
「工藤先輩は、調べたんですか?」
「もちろん。僕がこの中庭整備のプロジェクトを立ち上げた
理由。それは……」
「はい」
「最初は、荒れてるからきれいにしたいなっていう単純な動
機だったの。でも、今言ったみたいに、なんでそんな長い間
ずっと荒れたままだったんだろうって思ってさ」
「ふうん」
「最初は美化のはずだったのが、謎解きになったんだ」
「わ! 知らなかったですー」
「でしょ?」
そう。そこから僕の戦いが始まったんだよね。
校長との条件闘争、事務長の説得、片桐先輩とタッグを組ん
での鎮護、そして羅刹門の封鎖。
ただそこにあるだけで、僕らには何もしない、出来ないはず
の中庭が、まるで僕らに挑みかかる化け物みたいに感じたん
だ。
ニュメントの真下に埋められてた宇戸野さんの髪を探し出し
てるんだ。
マイナスの念を帯びた髪が、モニュメントの抑えの力を削い
でるって言ってたなあ。
「今はもうそんなのはないよね。げっ!!」
何気なくモニュメントの中をひょいと覗き込んで、心臓が止
まるかと思ったくらい驚いた。
「て、手紙ぃ!?」
何の飾りけもない白い角封筒。口が開かないように小石が乗
せられてるってことは、封がされてないのか。
「うーん……」
みのんのことだ。ここには毎日来てるはず。
中庭の中にゴミが落ちてないかどうか、厳しく見回っている
だろう。こんな目立つものを見逃すはずがない。
つまり、昨日みのんがここを出て、今日僕がここに来るまで
の間に置かれたものだろう。
なんのため?
僕には一つしか思い浮かばなかった。
「みのんへのラブレターだろなあ」
みのんは、ここにいる間は女の子と付き合うつもりはないと
はっきり宣言している。
それでも。それでもなお、みのんに想いを寄せる女の子は跡
を絶たない。
そりゃそうさ。人の気持ちだけは、理屈じゃないもの。
好きも嫌いも感覚的なもので、それはどうしてって聞かれて
も困る。
そして。
当たり前だけど、好きってなったらどうしてもそれは伝えた
くなる。伝えないと、両想いになれるチャンスがないもの。
もちろん、伝えたって玉砕しちゃう可能性の方がずっとおっ
きいけどさ。それでも、ね。
なぜ、モニュメントの真下に置いたか。
願をかけたんだろなあ。
自由、創造、友情を象徴するモニュメントの三本の柱。
それぞれの力が決意を後押ししてくれる。
そしてモニュメントの真下に置けば、他の場所と違って見回
りに来たみのんの目に確実に留まるんだ。
確実にってことなら下駄箱の中に置くのが一番だけど、そこ
はライバルが多いし、どうしてもラブレターを仕込むアク
ションが目立っちゃう。こっそりが出来ない。
見せつけるように堂々とっていうデモンストレーションは、
そういうのが大嫌いなみのんへのアピールとしては、最低の
策になっちゃう。
「むぅ」
それはいいけど。
どうするか、だよね。
ただのゴミとして僕が処理してもいいけど、中身が何かあた
りが付くからそれはちょっとなあ。
しゃあない。見なかったことにして成り行きに任せるか。
僕は、見下ろしていたモニュメントの台座から視線を外して、
そっと離れた。
「ふうっ」
僕が中庭入り口の水盤のところまで戻ったら。
一年生の部員らしい女の子が、顔を伏せたままこそっと近付
いてきた。
色白で小柄。派手な雰囲気はないけど、かわいい系だ。
かっちんがむふふと喜びそうなタイプ。
「あの……工藤先輩」
「こんにちは。当番?」
「はい」
「ええと、ごめん。一年生の部員は人数多いから、まだ全部
は覚えきれてないんだ。君は?」
「渡辺です」
「渡辺さんか。お疲れさま」
「あの……」
「なに?」
「み、見ました?」
その子が、おずおずとモニュメントを指差す。
「あるのは分かったけど、中は見てないよ」
ほっとしたように、その子が顔を上げた。
「マイアーに、だろ?」
「う」
返事は返ってこなかったけど、多分そうだろう。
「あいつの基本姿勢は知ってるよね」
「……うん」
「それが分かってるなら、いいんじゃない?」
「そうなんですか?」
「だって、ずっと抱えてるって苦しいじゃん」
「は……い」
僕は、もう一度中庭をぐるっと見回す。
塞がった鬼門。負の感情が吹き溜まりやすい危険な場所。
羅刹門の亀裂が封鎖されたって言っても、この中庭の危険な
性質が全て解消したわけじゃない。
ここにしか捨て場のない念が吹き溜まると……。
いつかまた、不幸の再生産が始まりそうな気がする。
それは……いやだなあ。
僕は無意識にしかめ面していたんだろう。
渡辺さんが、それを気にしたみたいだ。
「あの……やっぱりダメ、ですか?」
「え?」
慌てて、振り返る。
「違うよ。君の手紙のことじゃないの。ここの、この中庭の
変な性質のこと」
「へっ?」
今度は、渡辺さんがすっとんきょうな声を上げた。
「ははは。渡辺さんは、荒れてた中庭を僕らが整備した。そ
う先輩たちに聞いてるでしょ?」
「はい」
「じゃあさ。なんでずっと荒れたままだったと思う?」
「あ……」
ぽかんと口を開けて、渡辺さんも庭を見回す。
「ははは。そういうのも一年の部員で調べてくれるとうれし
いかな。そうしたら、君たちがここを見る目が少しだけ変わ
るかもしれないね」
「工藤先輩は、調べたんですか?」
「もちろん。僕がこの中庭整備のプロジェクトを立ち上げた
理由。それは……」
「はい」
「最初は、荒れてるからきれいにしたいなっていう単純な動
機だったの。でも、今言ったみたいに、なんでそんな長い間
ずっと荒れたままだったんだろうって思ってさ」
「ふうん」
「最初は美化のはずだったのが、謎解きになったんだ」
「わ! 知らなかったですー」
「でしょ?」
そう。そこから僕の戦いが始まったんだよね。
校長との条件闘争、事務長の説得、片桐先輩とタッグを組ん
での鎮護、そして羅刹門の封鎖。
ただそこにあるだけで、僕らには何もしない、出来ないはず
の中庭が、まるで僕らに挑みかかる化け物みたいに感じたん
だ。
2018-08-17 00:01