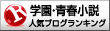三年生編 第77話(8) [小説]
まとめた荷物の中身をもう一度確認して、重光さんに携帯を
返してもらう。
二週間気絶していた携帯。
電源が入るかどうか不安だったけど、ボタンの長押しであっ
けなく意識を取り戻した。
「ふう……」
駅で、家に電話を入れることにしよう。
しゃらンとこには、家に帰ってから連絡、だな。
携帯をバッグにしまって、改めて重光さんにお礼を言う。
「二週間、お世話になりました」
「おう、斉藤にはもっと気合い入れろと言っとけ!」
うはあ。
「はあい」
「本番をしくじるなよ! そこでこけやがったら、根性座る
までどやし倒してやる!」
「がんばります!」
「当たり前だ!」
うん。
どこまでも真正面から覚悟を迫る。
今時珍しい、正統派のどやしだったなあ。
「では、これで失礼します」
ぺこ。
「おう」
短く答えた重光さんは、すぐに門扉を閉めた。
もう僕にはここにいる資格がない。そう言うかのように。
さてと。
日暮れが遅い夏。
それでも、街はずぶずぶと薄闇に飲み込まれていく。
家に着くのは深夜になりそうだ。
明日から日常が戻って来る。
でも……僕はもう、日常の上にのうのうと居座っていてはい
けないんだろう。
合宿は、これから来る変化のシミュレーション。
僕はそれをちゃんとこなせただろうか?
自問自答しながら。
街灯が灯り始めた駅までのゆるい坂道を、ゆっくりと歩いた。
−=*=−
「母さん? 講習の日程は無事終了。これから帰るわ」
「どうだった?」
「充実してたよ。進路関係のことも進展あり。帰ってからゆっ
くり話する」
「分かったー。今日は遅くなりそう?」
「九時過ぎになるかな」
「ああ、それでもそんなものなのね。気をつけてね」
「へえい」
ぷつ。
怖いくらいにいつも通りだった。
ってことは……。
僕のこと以外に、何かもっと気になることが起こったんだろ
う。そして、僕はそれが勘助おじさんのことだとしか思えな
かった。
父さんにとって、勘助おじさんは養親と同じ位置付けだ。
もちろん母さんも、おじさんにはとてもかわいがられてる。
二人とも気が気でないだろう。
僕は、むしろさゆりんの方が気になってる。
信高おじちゃんと衝突して、家を飛び出した。
その後は失うことばかりで、何一ついいことはなかったと思
う。
本当なら、おじさんおばさんや健ちゃんがちゃんと寄り添っ
てケアしてあげなければならない。
でも、みんな勘助おじさんの容体が気になって、さゆりんに
目を向ける余裕がないんじゃないかな。
……本当に心配だよ。
返してもらう。
二週間気絶していた携帯。
電源が入るかどうか不安だったけど、ボタンの長押しであっ
けなく意識を取り戻した。
「ふう……」
駅で、家に電話を入れることにしよう。
しゃらンとこには、家に帰ってから連絡、だな。
携帯をバッグにしまって、改めて重光さんにお礼を言う。
「二週間、お世話になりました」
「おう、斉藤にはもっと気合い入れろと言っとけ!」
うはあ。
「はあい」
「本番をしくじるなよ! そこでこけやがったら、根性座る
までどやし倒してやる!」
「がんばります!」
「当たり前だ!」
うん。
どこまでも真正面から覚悟を迫る。
今時珍しい、正統派のどやしだったなあ。
「では、これで失礼します」
ぺこ。
「おう」
短く答えた重光さんは、すぐに門扉を閉めた。
もう僕にはここにいる資格がない。そう言うかのように。
さてと。
日暮れが遅い夏。
それでも、街はずぶずぶと薄闇に飲み込まれていく。
家に着くのは深夜になりそうだ。
明日から日常が戻って来る。
でも……僕はもう、日常の上にのうのうと居座っていてはい
けないんだろう。
合宿は、これから来る変化のシミュレーション。
僕はそれをちゃんとこなせただろうか?
自問自答しながら。
街灯が灯り始めた駅までのゆるい坂道を、ゆっくりと歩いた。
−=*=−
「母さん? 講習の日程は無事終了。これから帰るわ」
「どうだった?」
「充実してたよ。進路関係のことも進展あり。帰ってからゆっ
くり話する」
「分かったー。今日は遅くなりそう?」
「九時過ぎになるかな」
「ああ、それでもそんなものなのね。気をつけてね」
「へえい」
ぷつ。
怖いくらいにいつも通りだった。
ってことは……。
僕のこと以外に、何かもっと気になることが起こったんだろ
う。そして、僕はそれが勘助おじさんのことだとしか思えな
かった。
父さんにとって、勘助おじさんは養親と同じ位置付けだ。
もちろん母さんも、おじさんにはとてもかわいがられてる。
二人とも気が気でないだろう。
僕は、むしろさゆりんの方が気になってる。
信高おじちゃんと衝突して、家を飛び出した。
その後は失うことばかりで、何一ついいことはなかったと思
う。
本当なら、おじさんおばさんや健ちゃんがちゃんと寄り添っ
てケアしてあげなければならない。
でも、みんな勘助おじさんの容体が気になって、さゆりんに
目を向ける余裕がないんじゃないかな。
……本当に心配だよ。
三年生編 第77話(7) [小説]
「わ! 思ったよりきれいだー」
「そうなの。お寺の部屋だから、どんなにおんぼろかと思っ
たんだけど、空調ない以外は快適だと思う」
「網戸は?」
「置いてくよ。君が出る時には外してって。殺虫剤も置いて
くから」
「分かったー。助かるー」
「お盆過ぎたら夜は涼しくなってくると思うから、これまで
より快適だと思う」
「そう願いたいなー」
「門限あるから、遅くなるようなら重光さんに電話入れてね」
「おけー」
「携帯使えないから、必ずどっかに番号控えといてね」
「あ! そっかあ……」
「家との連絡も、重光さんのところからしか出来ない。そこ
んとこだけ要注意ね」
「わかつたー」
合宿慣れしているんだろう。
彼女の受け答えには、とまどいとか驚きみたいなものがほと
んど感じられなかった。
「あとは、何か質問ある?」
「ううん、特にない。あとはやってみて、だなー」
「そう思う」
「ねえねえ、工藤さん」
「なに?」
「ホームシックとか、なった?」
「なるかなあと思ったんだけど」
「うん」
「進路の悩みが深くて、それどこじゃなかったわ」
「へー……」
「一応決着付いたからいいけどね」
「そっかあ」
「心配?」
「ううん。わたしは、そういうの一切ないの。早く家出たい
なー」
「もしかして、それで関西?」
「そう。うちは両親がうっさいから」
「ははは」
「工藤さんは、大学は自宅から通うの?」
「いや、一応下宿の予定」
「そっか」
「志望校に入れれば、だけどね」
「そこは自宅から遠いの?」
「微妙。通って通えないことはないんだけどさ」
「ふうん」
「一度自分を家から切り離さないと、ダメになりそうな気が
すんだよなー」
「へー。親はうっさいの?」
「んにゃあ。さっさと独立してねーって感じ」
「いいなー」
「でも、口でそう言うほど乾いてない。うちは……どこかウ
エットなんだよね。一度ばらしてみないと、お互いにその影
響が分かんないって感じ」
「それなら、もっと遠くの大学がいいんちゃうの?」
「僕一人なら……ね」
「え? どゆこと?」
「彼女がいるからさ」
忠岡さんは、そこでぴたっと口をつぐんだ。
それまでは男同士でしていたような、さばっとした会話。
僕が『彼女』という言葉を出した途端に、彼女がどこかにか
ちんと鍵をかけたような気がした。
そうなんだよね。これが……怖いんだよ。
新しい出会いがどこで生まれるか分からないのと同じで、そ
れがすぱっと切れてしまうきっかけもどこにあるか分からな
い。
まあ、いいよ。
どっちにしても、僕は今日で終わり。
合宿の世界とは縁が切れてしまう。
あとは忠岡さんが、ここにいる時間を有効に使ってくれれば
それでいい。
「さて。それじゃ僕はこれで失礼します。後から分かんない
ことが出て来たら、重光さんに直接聞いてください」
「分かった。ありがとう」
「いえいえー」
「そうなの。お寺の部屋だから、どんなにおんぼろかと思っ
たんだけど、空調ない以外は快適だと思う」
「網戸は?」
「置いてくよ。君が出る時には外してって。殺虫剤も置いて
くから」
「分かったー。助かるー」
「お盆過ぎたら夜は涼しくなってくると思うから、これまで
より快適だと思う」
「そう願いたいなー」
「門限あるから、遅くなるようなら重光さんに電話入れてね」
「おけー」
「携帯使えないから、必ずどっかに番号控えといてね」
「あ! そっかあ……」
「家との連絡も、重光さんのところからしか出来ない。そこ
んとこだけ要注意ね」
「わかつたー」
合宿慣れしているんだろう。
彼女の受け答えには、とまどいとか驚きみたいなものがほと
んど感じられなかった。
「あとは、何か質問ある?」
「ううん、特にない。あとはやってみて、だなー」
「そう思う」
「ねえねえ、工藤さん」
「なに?」
「ホームシックとか、なった?」
「なるかなあと思ったんだけど」
「うん」
「進路の悩みが深くて、それどこじゃなかったわ」
「へー……」
「一応決着付いたからいいけどね」
「そっかあ」
「心配?」
「ううん。わたしは、そういうの一切ないの。早く家出たい
なー」
「もしかして、それで関西?」
「そう。うちは両親がうっさいから」
「ははは」
「工藤さんは、大学は自宅から通うの?」
「いや、一応下宿の予定」
「そっか」
「志望校に入れれば、だけどね」
「そこは自宅から遠いの?」
「微妙。通って通えないことはないんだけどさ」
「ふうん」
「一度自分を家から切り離さないと、ダメになりそうな気が
すんだよなー」
「へー。親はうっさいの?」
「んにゃあ。さっさと独立してねーって感じ」
「いいなー」
「でも、口でそう言うほど乾いてない。うちは……どこかウ
エットなんだよね。一度ばらしてみないと、お互いにその影
響が分かんないって感じ」
「それなら、もっと遠くの大学がいいんちゃうの?」
「僕一人なら……ね」
「え? どゆこと?」
「彼女がいるからさ」
忠岡さんは、そこでぴたっと口をつぐんだ。
それまでは男同士でしていたような、さばっとした会話。
僕が『彼女』という言葉を出した途端に、彼女がどこかにか
ちんと鍵をかけたような気がした。
そうなんだよね。これが……怖いんだよ。
新しい出会いがどこで生まれるか分からないのと同じで、そ
れがすぱっと切れてしまうきっかけもどこにあるか分からな
い。
まあ、いいよ。
どっちにしても、僕は今日で終わり。
合宿の世界とは縁が切れてしまう。
あとは忠岡さんが、ここにいる時間を有効に使ってくれれば
それでいい。
「さて。それじゃ僕はこれで失礼します。後から分かんない
ことが出て来たら、重光さんに直接聞いてください」
「分かった。ありがとう」
「いえいえー」