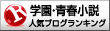【SS】 制約 (上野千鶴、リドルのマスター) (二) [SS]
予想以上においしいココアにすっかり満足したわたしは、マ
スターにお礼を言った。
「ほんとにおいしいココアでしたー。久しぶりだなー」
「ご自宅では飲まれないんですか?」
「まだ子供が小さいので、ココア作ってる余裕がないんです」
「ははは。じゃあ、今日は息抜きですね」
「はい。お義母さんが、たまには気晴らししないと保たない
よって」
「そりゃそうだ」
家族以外の人とまともに会話したのって、いつ以来かな?
わたしは、おおらかなマスターの雰囲気に安心したんだろう。
まるで、感情をせき止めていたでっかいダムが決壊したみた
いに、愚痴をどおっと吐き出してしまった。
子供はかわいいけれど、自分の時間がまるっきりなくなって、
家に閉じ込められてるみたい。
心の余裕を失って、ストレスのはけ口をどこにも見つけられ
ない。
子供見ててあげるから週に半日くらいは気晴らししなさいっ
ていう義母の提案は嬉しかったけど、だからと言って遊ぶわ
けにはいかないし。
仕事したいけど、そんな週に半日だけのバイトなんかどこに
もない。
愚痴をこぼしているうちに、せっかく暖かいココアで解れた
心が、またささくれ立ってきた。
黙ってうんうんとわたしの愚痴を聞いていたマスターは、思
いがけないことを言い出した。
「うちには、去年まで佐竹さんていう看板娘がいたんだけど
ね。その娘(こ)はここを卒業してしまったんです」
「はい?」
マスターがわたしの話と関係ないことをいきなり言い出した
から、ぎょっとした。
「あ、あの?」
マスターが、店の一角を指差した。
『女性アルバイト募集 勤務条件は応相談』
「……えと」
「佐竹さんの後で、誰かフルタイムで働ける人が欲しかった
んだけど、バイト代も安いし、無理は言えない。今は、前川
さんと曽田さんていう女性二人でローテしてます」
「でも、週一の半日だけじゃあ……」
「いや、その日を他のバイトさん二人の完全休養日に出来る
から。シフト回すのに、余裕を持てるんですよ」
「今は、その枠をどうされてるんですか?」
「この商店街の床屋の娘さん、高校生なんだけど、その子に
無理を言ってピンチヒッターを頼んでるんです。でも、受験
生だからね」
「あ、そうかあ……」
「半日でもすごく助かるんですよ」
確かに、わたしにとってこれ以上好条件のバイトなんか見つ
かりそうになかった。
わたしが気になったのは、なぜ常にアルバイトさんを入れて
るのか、だ。
店内の雰囲気を見ても、大勢のお客さんで溢れ返ってるって
感じじゃない。
マスター一人でも十分やっていけそうに見えるんだけどなあ。
そう、わたしはがっつり警戒したんだ。
「あの……」
「はい?」
「マスター一人じゃ切り盛り出来ないってこと……なんです
か?」
「そうなんだよね」
少し腰を曲げたマスターが、顔をしかめた。
「僕は前、少林寺をやってたの。そっちで師範の資格を取っ
て食ってくつもりだったんだけど、腰をやっちゃってね」
あっ!
「今は、日常生活には辛うじて支障がないってレベルなんで
す。でも、重いものを持ったり、中腰の姿勢を長時間続けた
りは出来ないんですよ」
「それで、ですか!」
「給仕(サーブ)があるから、僕一人だと半日が限界。どう
しても……ね」
そりゃあ……大変だあ。
「うちはコーヒー、紅茶だけじゃなくて料理も出してるから、
半日でも決して楽じゃありませんよ。それでもいいですか?」
「子供の抱っこして攻撃よりは楽ですよー」
「わははははっ!」
からっと笑ったマスターは、ぐるっと店内を見回しながら言っ
た。
「制約ってのは誰にでもありますよ。僕だって、まさかこん
な制約がかかるなんて思ってもみなかった」
「……」
「でも、それなら制約の中でどうやりくりするかを考えない
とね」
マスターが、空になったわたしのマグカップを指差した。
「うちのココアが他よりいい材料を使ってるってことはない
です。どこにでもある牛乳とココアパウダー、砂糖の組み合
わせ。店の経営コストを考えたら、それしか出来ないです」
「はい」
「それなら、丁寧に作る。心をこめる。僕にはそういう方法
しかないんですよ。自分の手と頭を使うのはタダですから」
「!!」
そっか!
「上野さんも、たった半日っていう制約を、制約のままにし
ないでくださいね」
マスターは目尻を下げて笑った。
でも、それは必ずしも好意の笑いではなかったと思う。
今日は黙って愚痴を聞いてやったけど、他のお客さんに向かっ
てそれを垂れ流したら承知しないぞ!
そういう……どやし、だ。
うん。
わたしは、家庭に入ってからぶったるんでいたんだろう。
主婦や母親としてするべきことは、絶対に手を抜いていない
と思う。
でも意識が甘ったるかったんだ。あの……ココアみたいに。
「がんばります! よろしくお願いします」
「こちらこそ。じゃあ、早速仕事の説明をします」
わたしがバイトを承けた途端に、マスターの口調ががらっと
変わった。
マスターにかかっているのと同じ制約。
わたしは、接客の技量でそれを乗り越えないとならない。
椅子から飛び降りて、カウンターの向こうに移動した途端に。
店内にいたお客さんの視線が、一斉にわたしに向けられた。
お客さんに笑顔で接すること。
わたしが店員をしていた時に、最初に叩き込まれたこと。
思い出そう。基本中の基本だ。
「上野です。よろしくお願いします!」
まだぎごちない笑顔だったけど、お客さんはみんな頷いてく
れた。
よーし! がんばるぞー!
【SS】 制約 (上野千鶴、リドルのマスター) (一) [SS]
「ほんとにわたしでいいんですか?」
わたしは、マスターに何度も確認した。
マスターが提示してくれたのは、わたしには夢のような好条
件だったけど、本当にそれでいいのかが信じられなかったか
らだ。
「いや、僕の出した条件で承けてくれるなら、本当に助かり
ます」
−=*=−
二人目の子供が生まれてから、それまでの生活が一変した。
朝から晩まで育児と家事で振り回され続け、子供一人の時は
なんだかんだでまだ確保できていた自分の時間が、まるっき
りなくなった。
自分はのんびり屋だから、このくらいのストレスは平気よ。
夫にも親にもそう言って安心させてたけど、平気だっていう
ポーズすら取れなくなっていた自分の心の危うさに……愕然
とした。
家に閉じ込められたまま、ストレスのはけ口がどこにも見つ
けられない。
ストレスが爆発して、自分の子供に鬱憤をぶつけてしまうん
じゃないかって……すっごい怖かった。
わたしは、ぎりぎりまで追い詰められていたんだ。
お義母さんが、そんなわたしの窮状を一早く察してくれた。
「子供たちは見ててあげるから、週に半日くらいは外でしっ
かり気晴らししなさいな」
そう……提案してくれた。
わたしは本当にラッキーだったんだろう。
子供たちがいなくても、家事はしないとならない。
わたしがずっと家にいると、結局体も心も休まらない。
だから、お義母さんの申し出は本当に嬉しかった。
でも、ただお茶するとか買い物するとかだと、結局家のこと
が気になってしまう。
それに、子供をほっぽらかして自分だけが遊んでいるように
思えて、気軽に友達を誘えない。
全然気晴らしに……ならないんだ。
働きたい。
それは、お金のためじゃない。
わたしの気持ちを、家や子供のことからぱちんと切り替える
ためだ。
独身時代はずっと店員をやってて、接客には慣れてる。
接客している間は、お客さんに意識を集中出来るんだ。
他に何も考えなくて済む。
そういう時間が欲しい。どうしても欲しい!
でも、週に一回だけ、それも半日だけの勤務なんて、いくら
パートだって言ってもありえないでしょ。
せっかくお義母さんが提案してくれた息抜きが、空振りに終
わるかもしれない。目の前にチャンスがあるのに……。
わたしは、また追い詰められてしまったの。
そんな、世の中わたしに都合良くは出来てないよね……。
意気消沈したわたしがふらっと入った喫茶店。
そこが……リドルだった。
普段食料品とかを買い物する時には、大型スーパーに行くこ
との方がずっと多い。
でもわたしは、昔からの商店街で買い物するのが好きだった。
値段とかそういうことじゃなくて、人と人とが直接触れ合う
機会が必ずあるから。
魚屋の元気なお兄さん。
八百屋の強引なおじさん。
肉屋の仲のいい年配のご夫婦。
他愛ない会話であっても、そこで言葉をやり取りする楽しさ
があった。
そして、商店街のアーケードの中は車がほとんど通らなかっ
た。
子供連れで安心して歩けるっていうことも、わたしには嬉し
かったんだ。
リドルは、その商店街の中にある喫茶店。
前から気にはなってたけど、子供連れじゃ入れない。
でも、そこに興味があったからっていうことじゃなく。
わたしは、どこでもいいから逃げ込みたかったんだろう。
ドアを引いたら、ドアベルがちりりんと鳴って、その音にび
くっとした。
薄暗い店内には年配のお客さんが何人かいて、各々コーヒー
や紅茶を飲みながら新聞に目を通したり、本を読んだりして
る。入ってきたわたしを見る人は誰もいない。
ボックス席を一人で占有するのはあれかなあと思って、カウ
ンターの椅子に腰を下ろした。
「いらっしゃいませー」
マスターは、わたしよりかは年上っぽい、でも中年というに
はまだ若い男の人。
微笑を浮かべながら、サイフォンを組み立てていた。
「何にいたしましょうか?」
「ええと……ココア、出来ます?」
「大丈夫ですよ。ミルクとお砂糖はどうなさいますか?」
え?
「いえ、甘いのがお好きな方、あっさりがいいとおっしゃる
方、いろいろおられるので」
うわ……すごおい。
ちゃんと好みに調整してくれるんだあ。
わたしは、それでいっぺんにこのお店が好きになった。
「じゃあ、甘め、濃いめでお願いできます?」
「かしこまりました」
年季の入ったミルクパンに特濃牛乳が注がれ、コンロの細い
火でゆっくりと温められた。
大きめのマグカップにきび糖とココアパウダーを量り取った
マスターはスプーンで掬った牛乳を垂らして、それをしっか
り練り上げた。
牛乳に膜が張らないうちに鍋をコンロから下ろしたマスター
は、慎重にマグの中のココアペーストを溶き伸ばしていく。
手間が味の違いに出るコーヒーや紅茶とは違う。
たかが、ココアじゃないか。
ココアパウダーと砂糖とホットミルクを入れてがちゃがちゃ
かき回すだけでもココアは出来る。
でも、マスターはそうしなかった。
丁寧に、丁寧に、一杯のココアを作り上げた。
「お待たせいたしました。ゆっくり温まっていってください
ね」
「ありがとうございます」
その一杯のココアは。
かちかちに張り詰めていた心を緩めてくれるくらい、暖かく
てほっとする味だった。
【SS】 俺様 (曽田真弓、リドルのマスター) (三) [SS]
なんか、わたしがすごくわがまま勝手な人間だと決めつけら
れているような気がして不愉快だった。
「あの……」
「はい?」
「佐竹さんは……そうしてたんですか?」
「あはは」
マスターが苦笑した。
「みこちんは、どこまでも俺様だからね。一目見ただけで機
嫌がいいか悪いか分かる。客より偉い」
どてっ。な、なんつーか……。それでいいの?
「でもね、みこちんは戸を閉めないんだ。常時開けっ放しな
んだよ。それだけじゃない。人の戸を、壊してでも開けに行
くの。おせっかいで姉御肌」
あ!
「曽田さんは、みこちんをよく知らないから愚痴をこぼした
んでしょ? もしもう少し付き合いが深くなったら。相手が
見えて来たら。オブラートに包んだんじゃない?」
う……図星……だ。
「人によって自分の戸の開け閉めをがらっと変えちゃうって
ことは、周囲から見てなんだかなあと思われちゃうの。特に、
こういう客商売だとね」
「は……い」
「それなら、これこれこういう時には戸を閉めちゃうぞーっ
て自分から宣言しちゃった方がいい。俺様の部分は、最初か
ら見えてた方が分かりやすいの」
そ、そんな。
「でも、それをすぐやれっていうのは難しいよ。どこまでも
あけすけってのは、みこちんだから出来ること」
「はい」
「それなら、自分の戸を閉めちゃう前に、あなたの戸を開け
させてくださいって努力する方が、まだ楽でしょ?」
あ、そういうことか。
マスターのたとえは、すとんと納得出来るものだった。
わたしの表情の変化をじーっと見ていたマスターは、カウン
ターテーブルをぽんと叩いて、さっと立ち上がった。
「うちには飛び込みのお客さんは滅多に来ません。常連さん
ばかりです」
「そうなんですか」
「商店街の中の店だからね」
そっか。
「曽田さんは、ああいつものお客さんかで済ますんじゃなく
て、そういう常連さんの戸をちゃんと開けてくださいね」
「……はい」
「そうしたら、あなたの戸も必ず開けてもらえますから」
−=*=−
あんたは隠れ俺様。
後で、佐竹さんからずばっと言われた。
良し悪しじゃないよ。
見え見えでも隠れてても、俺様は俺様なの。
そういうキャラなんだって、自覚するしかないでしょ。
……返す言葉がなかった。
わたしが何を言ったって、したって、それで何が変わるわけ
でもない。
俺様のわたしは、さっさと自分の戸を閉めてしまったんだ。
順番が……逆だったね。
マスターや佐竹さんのアドバイスを受けて、わたしは常連さ
んの戸を開けようって決意したけど、その必要なんか何もな
かった。
新人のわたしに興味津々の常連さんたちが、無遠慮にわたし
の戸を開けようとしたからだ。
あはは、マスター。確かに楽ちんだわ。
これじゃあ、わたしが戸を閉めない限り楽勝じゃないの。
でも。
リドルでのわたしは、俺様になる必要がない。
戸を閉める必要がないんだ。
そして、リドルはわたしが居るべき場所じゃない。
ここは……わたしの場所じゃ……ない。
じゃあ、わたしはどこに行けばいいの?
「曽田さん、そろそろ上がりにしよう」
「はあい」
最後の常連さんが、ごっそさんと言い残して店を出た後、マ
スターは入り口ドアを施錠しに行った。
わたしは椅子を寄せて床を拭ける状態にする。
今日も、答えは出なかったな……。
「マスター」
「うん?」
「俺様っていうのは……まずいんですかねえ」
「それを、俺様の俺に聞くなよ」
マスターが、おいおいって感じで苦笑いした。
ええー? うそお! マスターが俺様あ?
「会社勤めすんのが嫌で、こういう店やることにしたんだか
らさ」
「ああ、そうかあ」
「みこちんの方が、俺様に見えてそうでもない。仕事での役
回りはわきまえてて、きちんとチームプレイをこなしてるか
らね」
「そうですよね」
「まあ、モチベーションをどうこさえるかの問題じゃないか
と思うけどね。だって、指図しなくても動くのは……」
マスターが、わたしを見てにやっと笑った。
「いつでも、俺様だけだからさ」
【SS】 俺様 (曽田真弓、リドルのマスター) (二) [SS]
わたしがリドルでバイトすることになったきっかけ。
それは、ひょんなことからだった。
会社を辞めて抜け殻みたいになってたわたしは、すぐに次の
仕事を探す意欲が湧かなくて、住んでたアパートを引き払っ
て実家に帰った。
家に戻ったところで、何かすることがあるわけじゃない。
親はいい顔しないし、わたしもどこかで踏ん切りを付けて次
の行動を起こさなきゃとは思ってた。
でも、会社という集団から弾き出されてしまったわたしには、
致命的な欠陥があるのかもしれない。
それが何かが全然分からなかったわたしは、完全に腰が引け
てしまったんだ。
少しだけ。もう少しだけ猶予が欲しい。
わたしは学生の時にちょこっとだけ習っていたウクレレを気
晴らしに弾いてみようと思って、錆びちゃってた弦を張り替
えるのに楽器店に行ったんだ。
そこで……レジにいた佐竹さんていう若い女性店員さんと仲
良くなったの。すっごい話しやすい、気さくな人だったから。
大学を中退して、その後三年半くらいフリーターをやって、
いつまでもフリーターじゃなあって、ここに就職した。
佐竹さんは、そう言った。
でも佐竹さんは、フリーターをしてたってことが信じられな
いくらい、しゃっきしゃき。
きびきびしてて、明るくて、冗談好きで。
まだお店で働き始めてそんなに経ってないはずなのに、他の
スタッフの人たちとすごく打ち解けていた。
そこに……わたしはちくりと痛みを感じたんだ。
わたしは、自分の欠陥に気付かなかったんじゃない。
それを考えたくなかっただけ。
同じセクションに苦手な人が何人かいて。
わたしは、その人たちとどうしてもうまくコミュニケーショ
ンが取れなかった。
陰口叩いたりとか露骨に嫌悪感を示したりとか、そういうこ
とはしなかったつもりなんだけど……わたしの苦手意識は以
心伝心で相手に伝わっていたんだろう。
そこから。
その小さな亀裂から、わたしの破滅が始まっていたんだ。
互いに距離を置く。
個人的な付き合いの場合ならそれはオトナな対応で、ちゃん
と機能するんだろう。でも仕事ならそうは行かない、
チームワークや役割分担がきちんと求められる職場でメンバー
間の連携が切れてしまうと、すぐに致命傷になる。
そして、緊張関係の要の部分にわたしが居た。
……そういうこと。
わたしがこのまま次の職に就いたら、また同じ失敗を繰り返
すんじゃないだろうか。それは……底なしの恐怖に近かった
んだ。
わたしは、その悩みを黙って抱えていられなかった。
佐竹さんとは知り合ったばかり。何の利害関係もない。
わたしは、そこで洗いざらいゲロしたんだよね。
そしたら、佐竹さんが意外なことを言った。
「わたしのはさあ。フリーターって言うよりリハビリだった
んだよね。曽田さんにも、それ必要なんちゃう?」
リハビリ……かあ。
佐竹さんはわたしに、佐竹さんが前に働いていたリドルとい
う喫茶店でアルバイトすることを勧めてくれた。
後釜はまだフィックスされてないはず。マスターは多分喜ん
で雇ってくれるよって。
正直、バイトするなら人とあまり顔を合わせないタイプの仕
事にしたかった。
でも、佐竹さんがリハビリが必要って言ったことが気になっ
たんだ。
わたしは思い切ってリドルに電話して、バイトをさせてもら
えませんかってマスターにお願いしてみた。
そうしたら、面接したいのでお店まで来ていただけませんか
と、丁寧な返事。
いつまでもうだうだ考え込んでいたってしょうがないよね。
わたしは……思い切ってトライしてみることにしたんだ。
閉店後の喫茶店。
マスターが淹れてくれた一杯のコーヒーを挟んで、面接が始
まった。
「曽田さんは、こういう給仕とか店員さんとかのバイトや仕
事の経験がありますか?」
「いえ……学生時代は親がバイトを許してくれなかったので」
「そうですか。じゃあ、そこからかな」
温厚で優しげなマスターが、わたしの差し出した履歴書に素
早く目を通してから、すぐに返してくれた。
間髪を入れずに、マスターが話し始めた。
「ええとね。ウエイトレスっていう仕事は、ものすごーく簡
単で楽です」
「は?」
「でも、同時にものすごーく厄介で、しんどい仕事なんです
よ」
マスターの目は、笑ってるみたいに見えて、笑っていなかっ
た。
「僕の仕事も含めて、飲食業はサービス業です。お客さんは
店を選べますが、店はお客さんを選べません」
「……そうですね」
「いろんなタイプのお客さんが来ます。全員が、あなたに好
意的なわけじゃありません」
「……」
「あなたが苦手な、嫌いなお客さんが来ても、帰れって言え
ません。いいですか?」
「はい」
「人間ですから、感情にでこぼこがあるのは当たり前です」
「ええ」
「でも、それをお客さんに押し付けたら、あなたがそれだけ
の人間だって思われるんですよ」
「……」
「何もかも我慢しろとは言いませんが、あなたの戸は最後に
閉めてくださいね」
「どういう……ことですか?」
「その分、お客さんの戸を開ける努力をしてください。それ
が僕のオーダーです」
【SS】 俺様 (曽田真弓、リドルのマスター) (一) [SS]
ぴぴっ! ぴぴっ! ぴぴっ!
これまでの習慣で、つい定時に鳴らしてしまう目覚まし。
それをぽんと叩いて止めて。
わたしは上半身を起こすと、大きな溜息を吐き出しながら両
手で顔を覆った。
「そっか……もう辞めちゃったんだよな」
せいせいしたって言えれば良かったんだけど、そんな心境に
はどうしてもなれなかった。
それがわたしの望んでいない職種、会社、環境であれば、わ
たしは喜んで言っただろう。
ああ、こんなクソなところ辞められて、ほんとにせいせいし
たって。
でも、その正反対。
どうしてもその業種に就きたくて猛勉強して資格を取って、
靴を何足も履き潰して会社回りして、入社出来た時にはこん
ないい会社なんか他にどこにもないって、本気でそう思って
たんだ。
それが……。
どこで歯車が狂っちゃったんだろう?
「……」
どんなに考えても、それがなぜかがよく分からない。
分かっているのは、わたしが社で完全に浮いてしまったとい
うこと。
その状態で仕事を続ける限り、わたしを中心に不協和音の波
紋が広がって全てが台無しになるっていう事実だけが、目前
に突き付けられていた。
わたしが、こうしてああしてって会社に指図することなんか
出来ない。
わたしが何をどう言ったところで、社がわたしへの見方を変
えることは決してないだろう。
そうしたら、わたしの出来ることは一つしかなかったんだ。
辞めるしか……なかったんだ。
「ふううううっ……」
「おはようございます」
「おはよう。今日もよろしくな」
「はい!」
朝の開店準備。
マスターは、テーブルと椅子のセッティングを済ませてもう
一度店内をチェックすると、入り口ドアのタグを『営業中』
に切り替えに行った。
まだお客さんが誰もいない静かな店内。
でも開店を待っている常連さんが、もうこっちに向かって歩
いている頃だろう。
わたしも、テーブルの上のメニューや飾られている花や小物
類をもう一度チェックして、お客さんの入店を待つ。
静かだけど、賑やかになる予感を孕んでいる。
緊張と期待が交錯する、不思議な時間。
その短い間に、わたしはなぜ自分がここにいるのかを繰り返
し自問する。
ここは……わたしが居るべき場所じゃない。
イルベキ バショジャ ナイ。
じゃあ、わたしはどこに居るのが正しいの?
それが分からない。見つからない。もどかしい。
ちりん!
ドアベルが鳴って、いつも一番乗りの中田さんのおじいちゃ
んがゆっくりと入ってきた。
「いらっしゃいませー! お早うございます」
「ああ、まゆちゃんお早う。コーヒーとトーストを頼む」
「いつものですね?」
「そう」
「ありがとうございます。マスター、お勧めコーヒーとトー
ストです」
「おっけー」
マスターがサイフォンのサーバーに水を注ぎ、自分自身を確
認するようにして見回すと、おもむろにヒーターのスイッチ
を入れた。
今日の仕事はここから始まるんだぞって、自分に喝を入れる
みたいに。
お湯が湧いてくるまでの間に、電動ミルで豆を挽く。
今日のお勧めはホンジュラスだったかな。コーヒーのかぐわ
しい香りがかすかに漂ってくる。でも、それはまだ予感だ。
漏斗に挽いた粉を入れたマスターは、サイフォンの受けにそ
れをセットすると、オーブントースターのダイアルをぐりぐ
り回してから、角食を厚めに切った。
じじじじじ……。
庫内の温度が上がるまでの間に、コーヒーカップをカウンター
に出し、お湯を注いで温める。
流れるような、淀みない手付き。
サイフォンの水はすでに上のポットに上がって、ぽこぽこと
軽快な音楽を奏でている。
それに合わせて、豆を挽いていた時とは違う甘いまろやかな
コーヒーの匂いが店内を満たし始めた。
ぱちん。
サイフォンのスイッチを切ったマスターが、トースターの蓋
を開けてさっとパンを置いた。
それから、パンの色付きを慎重に見計らってジャストのタイ
ミングで取り出した。
浅めの狐色に焼き上がったトーストを皿の上にさっと据える
と、小さなバターポットを添えてわたしに差し出す。
わたしがトレイの上にそれを乗せたら、熱々のコーヒーがと
くとくとカップに注がれた。
ああ……おいしそう。
「お待たせいたしました。本日のお勧めコーヒーとトースト
になります」
「ああ、いい香りだ。これがないと一日が始まらん」
手にしていた新聞を手早く畳んだ中田のおじいちゃんは、嬉
しそうにコーヒーを口に含み、それからトーストにたっぷり
バターを塗って、がぶっと噛み付いた。
「嫁さんが、バターは体に悪いからって塗らせてくれんのだ。
ったく……」
あはは。
だからって、ここで塗ったらだめだよー。おじいちゃん。
でも。
そういう繰り言すら、おじいちゃんにとっては一日を始める
ための大事な儀式になっているんだろう。
【SS】 ラテアート (前川路乃、リドルのマスター) (二) [SS]
「ははは。相変わらずハイテンポだよなあ」
「明るい方ですね」
「まあね。直情径行の姉御肌。怒らすと、すぐに拳が吹っ飛
んでくる」
マスターが肩をすくめた。
元気でいいなあ……。わたしは思わず愚痴った。
「ああいう方なら……すぐ気持ちを切り替えられるんでしょ
うね」
「いやあ」
それまでにこにこしていたマスターが、ふっと真顔になった。
「違うよ。あのタフなみこちんですら、三年かかったんだ」
「えっ!?」
「親に裏切られ、恋人に捨てられ、その心の傷が元で歌えな
くなった。子供の頃からの大事な夢。人生を懸けてた声楽を
諦めて、音大を中退したんだよ」
げ……。
「自分も含めて、信じられるもの、頼れるものが何もなくなっ
た。全てを失ったんだ」
「……」
「そのどん底から這い上がって、三年でここを卒業した。ほ
んとに大したもんだと思うよ」
「じゃあ、勉強っていうのは……」
「自分ばかり見てたって、答えなんか分かんないさ」
マスターが、わたしに向かってぴしりと言い据えた。
「ここに来るお客さんは、誰もが自分の人生を背負ってる。
それはきれいごとばかりじゃないよ。でっかい傷も、醜い感
情もあるんだ」
「でも、そのどろどろをしっかり見て、自分ならどうこなす
すかを考える。答えはそこから出てくるよ」
「まさに勉強さ。俺も毎日勉強してる」
「そうですか……」
マスターはそれ以上ごちゃごちゃ言わないで、カウンターの
後ろに戻ってコーヒー豆のローストを始めた。
そうか。焙煎香がきついから、お客さんが多い時には出来な
いもんなあ。
「ねえ、みっち」
じっとマスターを見ていたかなこが、短い溜息をついた。
「うん?」
「ああいう人にアドバイスをもらえるって、いいね」
うん。ここのマスターは、前のあの女たらしの男とは違う。
その口から綺麗事や甘い言葉が出てくることはない。
出てくるのは……どれもそのまま飲み込むには苦い言葉。
砂糖やミルクでぼやかさないコーヒーの苦さ。そのものだ。
「うん……そうね」
かなこは、この喫茶店はわたしにすごく合ってると言い残し
て、安心したように帰って行った。
わざわざわたしに会いに来てくれたかなこ。
でも、それはわたしを心配したからじゃないと思う。
きっとかなこには、わたしに何か相談したいことがあったん
だろう。
かなこがそれを切り出さなかったのは、わたしが甘ったれな
ままで全然変わってないのが分かっちゃったから。
共倒れしそうで、怖くて口に出せなかったんでしょ?
……情けない。後で電話しないとね……。
わたしは、空になった二客のコーヒーカップを見下ろした。
中身が飲み干されたコーヒーカップ。
そこにラテアートがあろうがなかろうが、中身は紛れもなく
コーヒーだ。
そしてかなこの心の中には、わたしの描いたラテアートより、
マスターの苦言の方がしっかりと印象付けられたんだろう。
わたしがそうであるように。
カップの縁をそっと指で弾いて、鳴らした。
ちん。
わたしは……ラテアートをしばらく封印しよう。
マスターが言うみたいに、混ぜ物なしでちゃんと自分ていう
コーヒーの味が分かるようにしないとだめだ。
苦さをいつまでもミルクと砂糖でごまかしていたら、また誰
かに騙されて食いものにされちゃうんだろう。
わたしは、同じ失敗を愚かしく繰り返したくない。
黒くて苦いコーヒーの液面に映る自分。
それを……きちんと見据えないとね。
−=*=−
閉店直後。
わたしはカップをきれいに洗って、きゅっきゅっと拭き上げ、
カップボードに収める。
「……」
一つだけ手元に残したカップ。
それにスチーマーで泡立てたホットミルクを注いで、ココア
パウダーで文字を記した。
カップをカウンターに置き、床にモップを走らせていたマス
ターに声を掛けた。
「マスター、お先ですー」
「ああ、お疲れ様」
裏口から店を出たわたしは、正面に回り込んでこそっと店内
を覗いた。
わたしの残したラテアートに気付いたマスターが、苦笑と共
にホットミルクをごくりと飲み干した。
それを見届けたわたしは。
星の瞬き始めた淡い夜空を見上げて、小声で呟いてみる。
「ありがとう、くらいならいいよね」
【SS】 ラテアート (前川路乃、リドルのマスター) (一) [SS]
クリーミーに泡立てられたミルク。
その上で、黒いコーヒーが自在に世界を描く。
描かれた絵は人を騙すみたいに、にっこりと微笑む。
世界はちっとも苦くなんかない。
甘い、夢のような世界なんだよと。
嘘ばっか。
そんなの、カップに口を付けたらすぐに崩れて消える。
確かに夢じゃない。
ラテアートの絵は現実にそこにある。
でも、そこにあるのに儚い。
あっという間に……崩れて消える。
そして、口の中に残るのは苦い苦い後味だけだ。
−=*=−
「うわあ! みっち、すごおい!」
「そう?」
「これだけでやってけるんじゃない?」
大学で仲の良かったかなこが、わたしのバイト先の喫茶店に
遊びに来てくれた。
卒業したあと一度も会ってなかったから、三年ぶり。
かなこには、学生だった時にもラテアートを見せてたけど、
その時はまだまだ下手っぴだったんだよね。
目をまん丸にしてラテアートを覗き込んでるかなこに向かっ
て、ぱたぱた手を振る。
「無理、無理。このくらいのラテアートなら、描ける人は山
のようにいるよ」
「へー、そうなんかー」
「それに」
わたしはカウンターの方を振り返る。
「マスターがこういうの嫌いなんだよね。だからここじゃやっ
たことないの」
「ええー? おしゃれなのにー」
「混じり気のないコーヒーそのものを、ちゃんと味わって欲
しいんだってさ」
「ふうん」
かなこが、わたしの肩越しにマスターの顔をちら見した。
「うるさ型?」
「そんなことないよ。優しい人。でも、こだわるところには
すごくこだわるの」
「なるほどねえ」
−=*=−
わたしがラテアートを描くようになったきっかけは、ささい
なことだった。
学生時代バイトしていたこことは別の喫茶店で、そこのあら
さーのマスターに惚れ込んだ。
おしゃれですごく聡明。いつも笑顔で会話にウイットが利い
てて、一緒に居てとっても楽しかったんだ。
そのマスターに、ラテアートの描き方を習ったの。
でも、マスターが手ほどきしてくれたのはラテアートだけじゃ
なかった。
世間知らずのわたしは、マスターが見せる聡明さや快活さが
女の子を呼び込むための単なる小道具だっていうことに、全
然気付かなかったんだ。
マスターの舌先三寸の口説き文句にかあっとのぼせて、ずっ
と一緒に仕事しようと思い詰めて、勤め始めたばかりの会社
を辞め、バリスタ養成校に入り直した。
マスターにはもう奥さん子供がいたことなんか、これっぽっ
ちも知らないで。
ああ……。
それは騙したマスターよりも、あっさり騙されてしまったわ
たしが悪いんだろう。
マスターにとっては、わたしなんか大勢いるつまみ食い用の
若い子の一人に過ぎない。
一方的にのぼせ上がってたわたしが大バカだっただけ。
わたしとの付き合いが奥さんにばれたマスターは、わたしを
首にして追い払った。
わたしに残ったのは、すぐに消えちゃうラテアート。
そして……いつまでも口の中に残る苦い味だけだった。
−=*=−
お友達が来てるなら、お客さんのピークは過ぎてるから落ち
着いてゆっくり話したらいいよ。
そういうマスターの勧めに甘えて、わたしはかなこの向かい
の席に腰を下ろした。
その途端にドアベルが派手に鳴って、ばたんと扉が開いた。
わたしと同じくらいの年かなあ。
いかにもエネルギッシュっていう感じの若い女の人が、息を
弾ませながら店にのしのしと入ってきた。
「うーす!」
「お! みこちん、お見限りぃ」
「わはは! ばたばた忙しくてさあ!」
「みたいだな。いいことじゃないか」
「まあね。あ、お勧めコーヒーと今日のケーキちょうだい」
「あいよ」
慌てて席を立って接客しようとしたら、お客さんが手を上げ
てわたしを止めた。
「ああ、いいって。今の時間はのんびりしてて。あたしもそ
うやってたから」
「あの……ここで働かれてたんですか?」
「そ。三年ちょっとね。マスター、あたしの後の人?」
「そう。みこちんみたいに、一人で何人前も出来る人はいな
いよ。今は三人シフトで回してるんだ。その一人。前川路乃
さん」
「シフトかあ。そうだよなあ」
頷いたお客さんは、わたしにぽんと話を振った。
「ここは働きやすいでしょ?」
「はい。そうですね」
「しっかり勉強してってちょうだい。あたしもたっぷり勉強
したからさ」
え? 勉強……って?
そのあとマスターと軽快に突っ込み合っていた女の人は、あっ
という間にケーキとコーヒーを平らげて、ごっそさんと慌た
だしく店を出て行った。
【SS】 歌姫 (佐竹美琴) (十八) [SS]
クリコンの余韻が静かに消えて。
今日は、年内最後の営業日だ。
音楽教室のスケジュールが組まれてない分、お客さんの出入
りは少なめで、わたしたちはいつもよりちょっとだけのんび
りムード。
店長は、在庫処分で空いたエレピのスペースにパイプ椅子を
置いて、展示してあったクラギの弦を張り替えてる。
お客さんがいなければ、そのまま演奏を始めちゃいそうなノ
リだ。でも自重して、鼻歌で済ませてる。
「ふんふんふん、ふふーん、ふふん、ふふふん……」
頭の中で演奏してるのは、バッハのパルティータかな。
Bach Partita No. 1 BWV 825
そうなんだよねー。
店長は、プロギタリストとしての道を諦めてからもギターを
捨ててない。
今でもそこそこ弾けるってことは、忘れない程度には練習し
てるんだろう。
でも、もうちょい突っ込むのか、もっと引くのか。
そこをあえて決めてないんだ。
音楽への向き合い方に余裕と自由度を持たせることで、人に
もそうしたらって勧めることが出来る。
わたしが店長を見てていいなあと思うのは、お勧めを自ら実
践してるとこなんだよね。
隠れた凄腕を自慢するでもなく、挫折の黒歴史を苦く吐き出
すでもなく、今の自分が関われる範囲の音世界をとても大事
にしてる。
店長を見てて、わたしもそういう生き方がいいなーと思うよ
うになった。
だから、わたしはもう歌わない。
声楽家としては、ね。
好きな歌を、好きな時に、好きなリズムと調で、好きなよう
に歌おう。
そうしたら、べらんめえなわたしでもいつかは新しい歌姫に
なれる時が来るんじゃないかなあ。
「佐竹さーん! お客さんが試奏用のサックス吹き比べたいっ
て言ってるから、試奏室開けたげてー」
レジの後ろでほけてたわたしは、串田さんの声で我に返った。
お、いかんいかん。仕事、仕事!
「はあい!」
くすくすくすっ。
「へ?」
がばっと立ち上がったわたしの耳元で小さな笑い声が聞こえ
て、慌てて周囲を見回した。
でも、誰もいない。
うん。
笑ったのはきっと、羽が生えて飛んで行ったわたしの歌姫な
んだろう。
ちぇ! ちょっかい出しに来やがったかあ。
歌うのは、笑い出したくなるくらい楽しいよーって言いに来
たんでしょ?
わたしは、手にした鍵束をウインドチャイムみたいにちゃり
ちゃりっと鳴らしながら、レジカウンターから出た。
それから。
虚空に指を突きつけて、文句をぶちかます。
「こら。笑うんじゃないの! 笑いたいのはわたしの方なん
だからさ。うふふふふっ!」

Always A Saint by Sara Hickman
(補足)
佐竹美琴は、いっきやしゃらがよくお茶しに行く喫茶店リド
ルのウエイトレスさんでした。歳は中沢先生のちょっと下く
らい、二十代半ばのからっとした明るいおねいさんです。
人にちょっかいを出したり、イジったりするのが大好きで、
いっきやしゃらはよく餌食になってましたね。(^m^)
一方で、超が付く負けず嫌いで気が短くて手が早い。怒らせ
ると、すぐにトレイやげんこが降ってきます。
そういうがらっぱちなところとは裏腹に、人の心の影や弱み
をよーく見抜き、それに同調しないで徹底的にどやします。
良くも悪くも裏表のない、直球一本やりの力技タイプです。
子供の頃は、中塚家の次男坊元広(もっくん)と同じ少林寺
拳法の教室に通っていたやんちゃ娘の美琴さんですが、目指
していたのは声楽家。
でも親と恋人の裏切りで深く傷付いた美琴さんは、そのショッ
クで人前で歌おうとすると声が出なくなる一種の失声症に陥
り、声楽を諦めて音大を中退してしまいました。
その後、少林寺の師範代だったリドルのマスターに誘われて、
ウエイトレスをやってたんですね。
いっきがリドルに頻繁に行くようになってから、いっきやしゃ
らだけでなく、中沢先生、かんちゃん、もっくん、長岡さん、
ばんこと、それぞれに傷や問題を抱えた人々が再起や自立を
模索し続ける姿を間近に見続けてきた美琴さん。
自分もそろそろ傷を癒す時期は終わったと再出発を決意して、
リドルのウエイトレスをやめます。
このお話は、その美琴さんが就職した楽器店でのハプニング
を軸に、過去の描写を極力排して、『今』を重ねる形で書い
たものです。
実にイジり甲斐のあるキャラなので、出来れば恋バナに持っ
て行きたかったところなんですが、本話ではあえてその要素
を外しました。
美琴さんが音楽に向き合う姿勢のひたむきさ、真剣さ。
それを……どうしてもピュアに書き切りたかったからです。
これから美琴さんがどのように音楽と付き合って行くにして
も、彼女はきっとその過程を楽しんでくれるんじゃないかな
あと。
そういう祈りを込めて、本SSを締めくくりたいと思います。
【SS】 歌姫 (佐竹美琴) (十七) [SS]
「浜草さんは、田手さんのサポが切れても大丈夫なの?」
わたしが心配そうな顔をしたのを見て、沢田さんが内々の事
情を明かしてくれた。
「そろそろ……ハマの方が限界だったんすよ。トシのサポー
トを重たく感じてたみたいで」
「あ、そうかあ。そっちかあ……」
「トシとの関係が対等(イーブン)じゃないから、ハマには
コンプレクスばっかどんどん溜まっていっちゃう。見てて、
痛々しかったです」
「少し時間と距離を置いた方がってことね?」
「そうっす。お互い、離れないと分からんこともあるでしょ
うし」
そうだよね。
これで完全に壊れちゃったってことじゃなく、バラして風を
入れる時間を取った、そういうことなのかもしれないね。
「ハマは、ネットの歌い手に専念するみたいです。わたしは
対人恐怖があるから、ライブとかやっぱ無理ってカミングア
ウトして」
「ああ、正直にげろったんだー」
「その方がいいだろ。無理はよくないよ」
店長がずばっと言い切った。
「バンドってのは生き物さ。誰かが嫌だ、しんどいって思っ
たら、そこから先には行けないよ」
「それに、フォーピースってのはソロイスト四人じゃない。
誰が欠けても困るんだ。俺らが代役やれちゃうってことは、
まだまだ煮込みが足んないのさ。解散はしゃあないよ」
「ははは。ほんと、そうですね。でも」
「うん」
「俺とヤマは、これからもコンビでやります。すんごい楽し
かったんで」
「いいんじゃない? 今度は君らがきっちりイニシアチブを
取ったらいいよ」
「そっすね。あ、それで」
「うん」
「クリコンで佐竹さんと一緒に歌ってた子。いいなあと思っ
たんで、誘ってみようかと思ったんですけど。芽があります
かね?」
「ああ、千賀さんね。ボーカル張ってた学バンが解散したか
ら、今はフリーだよ」
「お!」
「でもなあ」
店長が腕組みして苦笑した。
「彼女がうんと言うかなあ……」
「え?」
「論より証拠さ。彼女のスタジオライブの音源があるから、
聞いてみたらいいよ」
そう言って事務室に引っ込んだ店長が、一枚のCDを持って
戻ってきた。
「学バン解散前の、最後のリハの音源。リハって言っても、
観客いるから一切手抜きなしのマジだよ」
それ以上何も説明しないで、CDプレイヤーにCDを突っ込
んだ店長が、沢田さんにヘッドフォンを渡した。
なんだろうっていう表情で、受け取ったヘッドフォンを装着
した沢田さんは、店長がプレイボタンを押した途端に派手に
ずっこけた。
「ぐわあっ!」
ひっひっひ。オープニングからジュダスプリーストのペイン
キラーだもんなあ。全開だ。
千賀さんは、自分がメイン張る時にはウルトラギャオスにな
るからねい。
気合い爆裂になった千賀さんは、はんぱじゃないぞお。
冷や汗をだらだら流しながら聴いていた沢田さんは、ヘッド
フォンを外してこめかみを押さえた。
「佐竹さんのオペラ以上に信じられないっす」
ぎゃははははははっ!
店長と二人で、腹を抱えて大笑い。
「ひっひっひっひっひー。とってもそんな風には見えないで
しょ?」
「音圧高あ!」
「でもね。彼女はそう出来るように、がっつり鍛えたんです
よー」
「え?」
「歌い始めた頃の千賀さんは、浜草さんと同じよ。透き通る
ような声。まさにエンゼルボイスだったけど、ものすごく線
が細かったの」
「うわ……」
「それなのに縦ノリ系で無理に声出そうとして、一発で喉潰
して」
「ぎょえええっ!?」
「そこから地味ぃにボイトレで鍛え上げてきたの。彼女は、
見かけによらず、すっごい根性あるんですよ」
「そっかあ……」
「自分のキャパをしっかり広げておかないと、こんな風に歌
いたいっていうイメージは表現出来ないです。シャウターは
上手に絞ればウィスパーになれるけど、その逆は出来ません
から」
「うーん、確かにそうですね。コンサートの時には、上手に
コントロールしてたものなあ……」
「声量や声質だけでなくて、選曲もそう。彼女はがっつり声
が出せるハードロックが好きなんだけど、それだけじゃ幅が
出ない。静かなバラードや軽いポップス系にもちゃんとチャ
レンジしてるし、歌い切れます。でもね」
わたしは、持ってたボールペンでレジ台をぽんと叩いた。
「MCでも言ってたと思うけど、彼女は自分の好きなように
歌いたいの。自分を押さえ込んで歌うより、自分を残らず出
し切りたい。それが今の千賀さんなの。だから、そう出来な
い条件ならうんと言わないと思う」
「そっかあ……残念だなあ。あ、佐竹さんは?」
そう来ると思ったんだ。
思わず苦笑いしちゃった。
「わたしはダメよー」
「どうしてですか?」
「歌姫が出て行っちゃったからね」
【SS】 歌姫 (佐竹美琴) (十六) [SS]
「無理だろ」
店長が、一刀両断ずんばらりん。情け容赦なし。
「彼女が歌うということを自己表出の手段としてしか使わな
い以上、曲の中には入り込めても世界は作れない。残念だけ
ど、彼女はずっと一番の歌詞止まりだと思うよ」
懐の深い店長にしては、ずいぶんあっさりと切り捨てたなあ。
でも店長の次の言葉を聞いて、わたしは納得した。
「歌にこだわり過ぎさ。浜草さんも田手さんもね」
あ、そういうことかあ。
そこも……かつてのわたしと同じだ。
「俺がギターなしで、そして佐竹さんが歌なしでちゃんと毎
日暮らせてるように、自分の生き方を楽しくする方法なんざ
山のようにあるよ。そいつをちゃんと使わんのは損さ」
わははははっ!
思わず大笑いしちゃった。
うん。確かにそうなんだよね。
「店長」
「うん?」
「そう考えられるようになるには、時間が要りますよー。わ
たしは三年かかりました」
「時間だけかい?」
「いえ、もちろんサポーターは必要だと思いますけど、浜草
さんにはもういるでしょ?」
「はははははっ! そうだな」
事故の時。
浜草さんを置いて田手さんだけがここに来ることは可能だっ
たし、バンマスとしてはその方が正解だったと思う。
だけど田手さんにとっては、CP4と浜草さんなら彼女の方
が優先だったんだ。
それは大山さんや沢田さんにとっては、無責任でなんだかな
あと思う判断だろう。
でも、すでに自立しているお二人と、不安定さが全然解消し
てない浜草さんなら、どうしても彼女のケアを先にしなけれ
ばならない。
自分のミュージシャン生命が断たれても、彼女を気遣うこと
を第一に考える。
それは、第三者から見ればバカみたいかもしれない。
でも、田手さんにとって彼女が全てである以上、外野が田手
さんの判断にとやかく言ってもしょうがない。
願わくば、そういう田手さんの底なしの優しさに、彼女がちゃ
んと気付いてくれますように……。
「さて。ピザもなくなったし。これでお開きにしますか」
店長があっさりと締めて、最初に立ち上がった。
みんなも次々に腰を上げて、帰り支度を始める。
「俺は会計済ませてから大山さんと沢田さんを送ってくから、
みんなは店舗の方頼むな」
「うーす」
「お疲れ様でした」
「お疲れー」
「お疲れさんしたー」
軽い反省会のはずなのに、わたしのせいでどっしり重くなっ
ちゃった。
そっちを反省しないとなー。思い込むとだあっと行っちゃう
悪い癖が直らない。とほほ……。
でも、店長のひょうひょうとした姿勢がかちこちになりそう
な空気をうまく解してた。
ほんとに動じないって言うか、乾いてるって言うか……。
でも店長のドライさは、わたしの思ってたのとはちょっと違
うかもしれない。
店長のは感情を出さないとか、隠すとか、繕うとか、そうい
うんじゃないんだよね。気持ちに余裕を持たせてて、感情の
出し方をいつも工夫してるんだ。
いつでもナマで直球のわたしと違って、自分をちゃんとプロ
デュースしてる。
そういうところは、ちゃんとプロ意識を持ってやってるんだ
よね。すごいわ。
There's A Light by Beth Nielsen Chapman
−=*=−
クリスマスコンサートを無事消化して、マスダ楽器は通常の
年末繁忙のみになった。
音楽教室の年末年始のスケジュール調整、教室の割り当て、
生徒さんたちの楽器購入やメンテの手続き。販促。
毎日ばたばたと忙しいけれど、それは商売としてはありがた
いこと。わたしたちが暇な方が困る。
レッスン予定表をチェックしていたら、伝票を鷲掴みにした
店長が無精ひげの伸びた顔をひょいと突き出した。
「どんな感じ?」
「今のところはノートラブルですー。あとは、リトミック科
の先生やお子さんにインフルが出ないことを祈りたいところ
ですねー」
「そうなんだよなあ。こればかりはなあ」
「みかんいっぱい食べて、予防するしかないですよ」
「俺は、みかん嫌いなんだよなあ」
「みかんの方が店長を嫌ってるんじゃないすかー?」
「なんだとう?」
「ぎゃはははっ!」
店長とばか話をしていたら、店に入って来たひょろっとした
若い男の人が、真っ直ぐレジに歩み寄ってきた。
「いらっしゃいませー」
「先日はありがとうございました」
あ! 沢田さんじゃん。帽子被ってないからすぐに分かんな
かった。
「こちらこそー!」
「一応、ご報告に」
うん。きっと解散報告だろう。
「解散……ですか?」
「はい。俺とヤマが抜けるってことじゃなく、完全に解散て
ことにしました。リピカさんにもそれで了承をもらって」
「引き止められなかったかい?」
「リピカさんは、ハマだけ欲しかったみたいっす。でも、そ
のハマが一番ダメなので」
沢田さんの苦笑いは、冗談抜きに苦そうだった。
やっぱ解散かあ……。
寂しいけど。わたしには最初から、そうなるんじゃないかっ
ていう予感みたいなのがあった。
CP4のような魅力も実力もあるバンドが、なぜ仮契約のま
まだったのか。
店長だけじゃない。芸プロの担当者もまた、繊細さの裏にあ
るひ弱さが最初から気になっていたんだろう。
CP4は、リーダーが強烈な個性でみんなをぐいぐいリード
するバンドじゃない。互いにこっそり肩を寄せ合うような、
ふわっとしたユニットだったんだ。
バンドとしての求心力を保ち続けるには、田手さんは優しす
ぎたし、浜草さんは弱すぎた。そして、大山さんと沢田さん
は、最初からサポートしか出来なかった。
誰かが突出しないからまとまりはいいけど、揺るがない精神
的支柱がなかったんだ。
ホールライブを経験することで一皮むけて、しっかりした芯
が出来れば『仮』は取れたのかもしれない。
でも……ライブのプレッシャーに浜草さんが耐えられなかっ
たんだろう。
I Know You By Heart by Eva Cassidy